★メディア掲載情報・寄稿 etc [最終更新:2018.8.09]
2018.08.09
<最新情報>
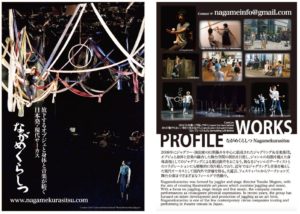
<過去のメディア掲載>
- 2018/8/9 The Japan Times 取材記事
- 「Could Japan have its own Cirque du Soleil?」
『うらのうらは、』
- 2018/8/5 定年時代 8月上旬号(公演情報)※朝日新聞折込誌
- 2018/8/5 しんぶん赤旗 日曜版 芸能短信(公演情報)
- 2018/8/3 公明新聞 文化面「イチ押し」記事
- 2018/8/2 シアターガイド 9月号渋谷エリア扉ページ(公演情報)
- 2018/6/5 演劇動画ニュース「エントレ」
- 「子供と楽しむ現代サーカス! ながめくらしつ『うらのうらは、』…」
- 2018/5/29 朝日新聞デジタル
- 「身体と物と音楽が描く日本発・現代サーカス…」
- 朝日新聞 2017年10月 ※国内で活動している現代サーカスカンパニーとして紹介
- European Network Circus and Street Arts Circostrada 日本視察レポート 2017年
- The Dance Times 2017年1月 ※ダンサー月間ベストテン選出:2016年12月
- 演劇動画ニュース「エントレ」 2016年12月 ※動画記事
- ステージナタリー 2016年12月
- シアターガイドweb 2016年12月
- 公明新聞 2016年12月
- 朝日新聞デジタル 2016年12月
- Hors les murs『100年サーカス(演出:目黒陽介)』掲載
<批評・推薦文>
- 『日本と「ながめくらしつ」と目黒陽介という存在』
田中未知子(瀬戸内サーカスファクトリー代表、仏国立大道芸サーカス情報センター日本特派員)
おおげさに書くつもりでなく、目黒陽介と、彼の作品「ながめくらしつ」との出会いは、現代サーカスに対する自分の方向性と立ち位置を完全に変えてしまったと言える。当初、現代サーカスの世界に飛び込み、ずぶずぶとのめり込んでいく中で、「外国の最高の作品を日本で紹介するのが自分の使命」と信じて疑わなかった。日本から作品を生み出し、発信していくなんて考えもしなかった。その考えを一発で叩き割ったのが、目黒陽介という存在だ。初めて「ながめくらしつ」を見た時に、この作品が日本に何かの扉を開いたのをはっきりと感じた。何かを生み出したいという苦しみとエネルギーと、鮮明すぎるイメージ。それは、サーカスアーティストの金井圭介が、フランスで「Gai-kotsu」という作品を生み出そうと試行錯誤していた姿とだぶるものがあった。
私はジャグリングの専門家ではないし、ジャグリング視点での作品評は他の方にお任せしたい。とりあえず、自分はいま「ながめくらしつ」評を書くのは不可能だ。なぜなら、新しい作品が出るたびに、これは途上だと感じるから。どこまでいくのだろう?目黒陽介の、創作に向かう傲慢で貪欲な目つきが、いつまでもこのまま続いて欲しいと願う。助成金も、アーティスト支援も決して多くないこの日本で、目黒のようなアーティストが生きられなかったら、日本全体に希望がもてないではないか!
日本人が創作し、世界に発信して初めて、本当の文化になる。それが可能だと初めて信じさせてくれたのが、目黒陽介である。だから、これからも生まれてくるだろう「ながめくらしつ」を見続けたい。そして、永遠に途上でありつづけて欲しい。
-
- 作品評『誰でもない/終わりをみながら(2014年)』 Twitter@NorikoshiTakaoより引用
乗越たかお(作家・ヤサぐれ舞踊評論家)
音楽集団×ジャグリング。おもろかった! ジャグリングの技は、まず安定して滑らかなことに徹し、ビックリさせるのは個人の技よりも演出でする事に重点を置く。二部構成の第一部はまさにそれで、集団でのお手玉は、超絶技巧ではないが故に作品として一皮むけている。
演出振付は目黒陽介。生演奏の坂本弘道と武藤イーガル健城という音楽的センスも光る。日本のジャグリングが作品を作っても、これまでは自分の技でビックリさせたいという意識が邪魔して、作品中でモザイク的にしか生かせないことが多かったが、これは可能性を感じる。
満席で立ち見まで。第二部でも、舞台美術を後半から全く変えて見せたり、布の前や最中にも演出がなされ、行き届いている。ただいまひとつインパクトが弱いなど課題は色々あり、これはまだ端緒だと思うが、期待したい。
-
- 作品評『起きないカラダ 眠らないアタマ(2012年)』
上島敏昭(大道芸人、大道芸研究家、東京都ヘブンアーティスト審査員)
夢ともなく現ともなく、ボールが飛び交い、体が舞うように動き回っている。このなんともとらえどころのない運動がジャグリングなのだろう。
演劇のように物語や、叙情にたよるのではなく、単純に音楽をバックにひたすらボールを投げて受け取り、棒を投げて受け取り、リングを投げて受け取りつづける。きわめて抽象的な作品。大道芸ではありがちな、大げさな身振りも、虚仮威しのような演技もない。そのためにボールやリング、棒などの動きが非常に美しい幾何学的な動線として見えてくる。また動線がみえたと思った瞬間に消えて、別の動線に変わっている。

